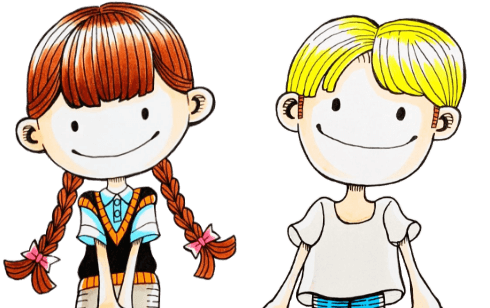消費税0%でも、消費者にとっては価格が高騰して消費税を0%にする意味がなくなる場合がある事を知っておかねばなりません。
税の仕組みについて調べてみました。
YouTube動画の内容に基づき、消費税の非課税取引(ゼロ税率を非課税として扱う場合)と免税取引(ゼロ税率を免税として扱う場合)の違い、および消費者と業者にとって負担にならない取引について解説します。
🧐 非課税取引と免税取引の違い
非課税取引と免税取引は、どちらも最終的に消費税を徴収しないという点では似ていますが、そのプロセス、特に仕入れ時に支払った消費税(仕入税額)の扱いに決定的な違いがあります。
| 項目 | 非課税取引(ゼロ税率反対派が想定) | 免税取引(ゼロ税率賛成派が想定) |
|---|---|---|
| 売上にかかる消費税 | 課税されない(ゼロ) | 課税されない(ゼロ) |
| 仕入税額控除 | できない [07:54] | できる [20:14] |
| 事業者の納税/還付 | 納税額はゼロだが、仕入税額が控除できず損をする [14:43] | 納税額がマイナスになり、仕入税額分が還付される [20:51] |
| 価格への影響 | 仕入税額分を価格に転嫁するため、値上げが発生する [09:03] | 価格転嫁の必要がなく、値上げは発生しない [20:33] |
| 消費者への影響 | 隠れた税負担(タックス・オン・タックス)が生じ、最終的な支払額が増える [13:27] | 税負担はゼロになり、支払額が増えない [23:31] |
| 🔑 最大の違い:仕入税額控除の可否 |
✴️非課税取引では、売上に対する消費税がない場合でも、仕入れ時に支払った消費税は控除(差し引き)することができません。
事業者はこの控除できなかった税額分を「払い損」とし、利益を確保するために販売価格に上乗せします。これが隠れた税負担(累積課税)となり、最終的に消費者が負担増となります [14:43]。
✳️免税取引では、売上に対する消費税がないにもかかわらず、仕入れ時に支払った消費税の控除が認められます。
売上税額(0円)から仕入税額を控除することで、事業者は還付金を受け取ります。この仕組みは、現在の輸出免税の還付金と同じロジックです [21:00]。
💰 消費者と業者にとって負担にならない取引
消費者にとっても業者にとっても、負担にならない取引は、免税取引です。
免税取引が負担にならない理由
免税取引の場合、税負担の連鎖が断ち切られ、最終的な消費者への負担がゼロになります。
✳️事業者側の負担ゼロ
メーカーから商品を購入した事業者は、仕入れで支払った消費税を国から還付してもらえます [20:51]。
事業者はこの税額分をコストとして価格に上乗せする必要がないため、値上げせずに販売できます [20:33]。
✳️消費者側の負担ゼロ
最終的な販売価格には消費税がかからず(ゼロ税率)、さらに隠れた税負担も含まれないため、消費者は消費税の負担が全くありません [23:31]。
取引全体を通じた最終的な税負担も、相殺されて合計0円となります [23:59]。
非課税取引の場合の負担
一方、非課税取引のロジックでゼロ税率を設定してしまうと、仕入れ税額控除ができないために事業者も消費者も両方が損をする結果になります [30:50]。
したがって、消費税ゼロ税率を導入するとして、食料品のように流通する物品に対しては、税の累積を防ぐために免税取引として設定すべきだと動画では解説されています [31:08, 32:34]。
業者にも消費者にも負担をかけない消費税のあり方は、免税取引を導入する事です。我々は、税のしくみを知って消費税0%が活かされ、生活に反映される税の在り方を理解する事が重要になります。